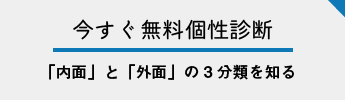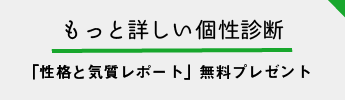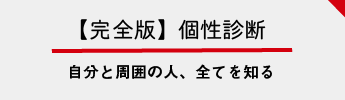『個性學メディア』を監修している村上燿市先生は、日本で唯一のシニアエバンジェリストであり、「個性學アドバイザー」の資格取得講座を開催できる唯一の先生です。
ご縁あって村上先生と出会い個性學を知った人たちは、人生で大きな変化を経験。
そして「個性學の素晴らしさを多くの人に伝えよう」と、門下から次々に個性學アドバイザーが誕生しています。
現在アドバイザーとして活躍されている方に、個性學を知ってから起こった人生の変化や、実践法、独自の活用法などをインタビュー。
今回は、個性學アドバイザー「城志向」編。
3分類を活用した独自の学習法で子どもたちを指導する久本慈光さんにお話を伺います。
この記事はこんな方におすすめ
- 「城志向」の方
- 「人志向」との接し方が知りたい
- 3分類に応じた学習法を知りたい
- 子どもの個性・才能を伸ばすヒントを知りたい
- 子どもとの関わり方に悩んでいる
- 自分に合った勉強法を知りたい大人
プロフィール
久本 慈光(ひさもと じこう)/個性學シニアアドバイザー
【略歴】
近畿大学附属豊岡高等学校で英語科教諭として勤務した後、2001年に学習塾「寺小屋」(兵庫県)を開設。
そのかたわら、非常勤講師として近畿大学附属豊岡高等学校、兵庫県立豊岡高校、出石高校などにも勤務。
一方でお寺を継承し、住職となる。
学習塾の経営に模索しビジネスへの学びを深めようと奮闘していたところ、2015年に村上燿市先生と出会い、ビジネスコーチングなどを受講。
2018年から村上燿市先生より個性學を学びはじめ、2019年に個性學シニアアドバイザー資格を取得。
「約30年の教師経験×個性學アドバイザー×住職」という唯一無二の経歴を活かして、独自の学習方針で中高生・受験生・保護者への指導とアドバイス、個性學講座を開催。好評を得ている。
個性學との出会い
慈光さんは長年教師をされていて、現在は学習塾を経営。
かつ、お寺の住職さんでもあるのですね。
個性學を学ぼうと思われたきっかけは?

慈光さん:
私は元々学校に勤めていたので、ビジネスには疎かったんですが、寺を引き継ぐことになり、寺をなんとか経営していかなきゃならない。
学習塾も経営していて…という頃、ビジネスのことを学ぶためにいろいろと模索していたら偶然、村上先生と出会いました。
出会ってからしばらくは、主にビジネスコーチングをしていただいていたのですが、2018年に個性學のことを教えていただいて。
当時は学生や保護者への対応などに四苦八苦していましたから、最初は
「個性學…? 生年月日でそんな多くのことがわかるなんて…」と怪しく感じましたね…
そんな簡単に相手のことがわかったら苦労ないよ?と(笑)。
でも村上先生も、コーチングで個性學を活用して成果を上げている、と。
同時に、信用していたT先生も「個性學はおすすめだよ」と背中を押してくださったので。
それが大きなひと押しになって「お二人が言うなら…」と思い、まずは個性學ONEから使ってみたんです。
モバイルアプリ「個性學ONE」に衝撃を受けた
個性學ONEを使ってみた印象は?

慈光さん:
ものすごい衝撃を受けましたよ!
本人からの聞き取りや診断をしなくても適性を判定できるので、
「もしこれが本当ならすごく使える!」と思いました。
私は塾で高校生を相手にしていますが、高校生は自分自身のことをまだよくわかっていませんから、本人への聞き取りや自己回答式の診断テストはあてにならないことも多かったんです。
受講初日に、個性學アドバイザーの資格取得を目指そうと決めました。
仕事で最大限に活用したいし、個性學セミナーも開催していきたかったので。
個性學が気になるけど迷っている人がいたら、「個性學ONEを使えば、個性學の良さはすぐにわかりますよ!」と伝えたいです。
自分が言われて嬉しい言葉は、相手も嬉しいわけではない
個性學を学びはじめてから、何か変化はありましたか?

辞めた生徒はほとんどが人志向だった
慈光さん:
個性學を学んだからこそ気付けたことがあります。
これまでにうちの学習塾を辞めていった生徒たちの個性を個性學ONEで見てみると、ほとんどが人志向だったんです。
うちの塾は「自分で」「必要以上に構わない」がモットーなんですが、
城志向の僕が最適と思っていた指導方針は、人志向の子たちには物足りなさを感じさせていたみたいなんです。
人志向の生徒たちが感じていた物足りなさ…とは?

城志向らしい先生の言動を「冷たい」と受け取る
慈光さん:
例えば、こんなことがありました。
個人面談で「日本史と世界史、どっちを選択したらいいですか?」と人志向の生徒に質問されたとき、
城志向の僕は「どちらでもいいよ」という答え方をしていたんですよ。
「どちらをとってもそんなに差はないし、一長一短あるから、君の好きなほうでいいよ」という意図です。
城志向の僕としては、良かれと思ってそう伝えていたんですね。
でも人志向の子は、「せっかく相談しているのに、どっちでもいい、自分で決めろって何なの?」って感じるみたいなんですよ。
なるほど…!
私も城志向ですが、城志向は「どちらでも好きにしていいよ」と言われたら、
意思を尊重されているように感じて嬉しいですよね。
「先生はどちらかを押し付けずに、フラットな目線でアドバイスしてくれている」と感じますよ。

慈光さん:
そうなんです、城志向はそう感じますよね。
人志向の子は、感じ方が全然違うんです。
個性學を学ぶ前は、そんなこと知らなかったですよね。
城志向の僕は、誠意を持って生徒に充分寄り添っているつもりでいる。
でも人志向の子は、城志向らしいアドバイスをする先生に対して「冷たい」と感じて、スーッといなくなるんです。
「親身になってくれていない」とか「私の気持ちをちゃんと汲んでくれていない」というような、目の前でシャッターをピシャッと閉められている感覚になるようです。
人志向の子たちは、「もっと親身になってほしい」「話を聞いてほしい」と思っていたんじゃないかなと、今ならわかりますね。
これは、「人志向」×「城志向」のあいだでの “あるある” のひとつです。
個性學を学んだから、「自分が言われて嬉しいことは、必ずしも相手も嬉しいわけではない」と知ることができましたね。
人志向に最適のアドバイス方法
「相手をきちんと理解する」の大切さを実感するエピソードですね。
人志向の生徒には、どうアドバイスするのが最適なのでしょう?

慈光さん:
人志向の子は、
- 話を聞いてほしい
- 親身になって寄り添ってほしい
- 「理由」の部分をきちんと理解したい
と思っています。
だから、こんなアドバイスを求めている。
「日本史の場合だったらこんなメリットがあって、こんなデメリットがあるよ。世界史の場合だったらこうだよ。そのあたりを加味して最終的には自分で決めたらいいと思うけれども、君にはこっちの方がいいかなと先生は思うよ」と。
「なぜそう思うか?」の理由を丁寧に説明してあげたうえで、最終的にどちらかを提案してあげるのがいいんです。
そして何よりも大切なのが、寄り添っている感じ。
話を聞いてあげる姿勢が大切です。
でも「君はどう思う?」といきなり聞かれても、「こう思う」と意見を言えないのが人志向です。
思うことはいっぱいあっても、唐突に聞かれると尋問みたいに捉えてしまったり、「言っていいのかな」「大丈夫かな」「こう思うけど本当かな」と感じたりするんですね。
だからまずは、「話していいよ」という雰囲気を作ってあげることが大切だし、先生はプロだよという安心感を与えるのもすごく大切なんです。
なるほど…!
人志向の生徒へのアドバイスをまとめると、こんなかんじですね。

【人志向の生徒には…】
- 話を聞いてあげる
- 親身になって寄り添っている感じが大切
- 話せる雰囲気が大切だが、「どう思う?」と唐突に聞かれても言えないので、まずは安心感を与えてあげる
- 「なぜ?」の理由をきちんと理解したがるから、丁寧に説明してあげる
- 最終的に提案をしてあげる
慈光さん:
それから人志向の子は、目標を決めるときも寄り添ってあげないとウロウロしてしまって決められない子が多い。
面談のときに先生が「これはどう?こっちは?」と色々な選択肢を提案すると、
人志向の子は「せっかく先生が言ってくれたから顔も立てなくてはいけないし…」と感じたり、「その選択肢もありだよな…」とじっくり考えてしまったりで、二転三転して志望校も迷ってしまうんですよね。
僕は個性學を学んだおかげもあって、人志向の生徒の話を聞いていたら「この子はまだ迷うだろうな」とか「ここに落ち着いたらもう大丈夫だろう」と感覚でわかるようになってきた。
なので、ここぞというタイミングで「その選択がいいと思うよ」と伝えてあげます。そうすると、人志向の子は決断できるんです。
こればっかりは、長年の教師経験で培った勘を掛け合わせた僕独自の経験です。
人志向には伝わらない⁈「自分との競争」
人志向さんへの対応法、勉強になります。
他に、個性學を取り入れてからの気付きはありますか?

慈光さん:
こんなこともありました。
うちの塾では、教室の一番目立つところに標語を掲げているんです。
僕が良いと感じた言葉を標語にしています。
その標語は「そろそろ他人との競争はやめて、自分との競争だ」。
城志向らしいでしょ(笑)。
そしたら人志向の子が「先生、意味がわかりません」って(笑)。
「なんで自分とまで競争しないといけないの?まだ競争するの?」ってボソッとつぶやいて…(笑)。
城志向の感覚だと、
「そうか、他人と比べなくていいんだ!自分の中で成長していればいいんだ」
「よし、自分なりに頑張るぞ!」
って奮うんですよね。
僕はそういう意図で、この標語を掲げたんです。
でも同じ言葉を見聞きしても、3分類「人・城・大物」が違うと、捉えた方って全然違うんですよ。
僕の真意を人志向の生徒に伝えたいなら、
「自分の成長をそのまま見つめよう」
と言い換えたら伝わるだろうなと、今ならわかります。
先生の意図をそのまま受け取れる生徒は、3分の1しかいない
本当に、3分類によって捉え方が全然違うのですね!

慈光さん:
全く異なりますよね。
ということは、授業で話していても、教師が話した意図通りに受け取っている生徒は3分の1しかいない、ということ。
残りの3分の2の生徒は、どこか何か勘違いをして理解している。
個性學を知らずに指導していたときの生徒には、申し訳ない気持ちになるくらい…個性學は重要なんですよ。
城志向らしさを活かした塾経営
個性學を学んでからは、人志向に合わせた塾経営をされるように?

慈光さん:
いえ。
個性學を知って、人志向の生徒への対応を改善してからは、こちらの対応への不満を理由にした退塾はほとんどなくなりました。
でも僕は、僕の個性・城志向らしさを活かして塾経営をしていこうと思っています。
だから、人志向の生徒は増えてはいません。
城志向にとって最高に居心地の良い学習環境
現在、うちの生徒の割合は、8割が城志向です。
なぜ城志向の生徒が多いかというと、うちの塾では、授業をしないから。
学校が終わってから好きなときに勝手に来て、好きなだけ勉強して、好きな時間に勝手に帰っていい、というスタイルでやっているんです。
城志向にとっては最高の環境ですね!

慈光さん:
そうでしょ(笑)。
城志向の子は、自分のペースで勉強しに来て、帰りたくなったらとっとと帰ります。
5分だけ先生の顔を見て帰る日もあれば、3時間勉強していく日もある。
今日の気分で。
城志向にとっては、他のどこよりも居心地が良い環境ですよね。
「類が友を呼ぶ」といった感じで、城志向ばかりが集まってきています。
生徒一人一人に合った「戦略」を教える
慈光さん:
それからうちの最大のサービスは、僕が一人一人に合わせて「戦略」を教えること。
「こうゆう順番で勉強するといいよ」
「この時期までにこのことを終わらせるといいよ」
「君の場合は、このやり方で勉強を進めるといいよ」とか。
この戦略手法が、そもそも城志向の生徒に合っているんです。
「教師歴30年×個性學アドバイザー」の経験から生み出した、3分類ごとの学習法
生徒一人一人に会った「戦略」というのは、
具体的にどのようなものですか?
もしよければ教えていただけないでしょうか…。

慈光さん:
私自身の30年の教師経験も加味して、3分類ごとに違ったアプローチで学習を進めさせています。
3分類それぞれに合った「勝ち方」があるんです。

人志向の生徒が成績アップする学習法
- テスト範囲の「基本問題のみ」を網羅
- テスト範囲の「中レベルの問題」を網羅
- 時間が余れば応用問題
人志向の生徒は、原理原則を理解したい。
だから「じっくり考えて、ゆっくり進もう」とアドバイスします。
教科書は通常、章ごとに「基本問題」→「中レベルの問題」→「発展問題」の順で書かれていますが、
教科書の順番どおりに人志向がテスト勉強をすると、すごく時間がかかります。
次の章になかなか進めないのです。
なのでテスト勉強の場合は、「まずは、テスト範囲の基本問題だけをしよう」とアドバイスします。
テスト範囲の基本問題だけを押さえる
→テスト範囲の中レベルの問題をやってみる
→テスト範囲の発展問題をする
と、螺旋を描くように積み上げていくのがいいんです。
「発展問題は時間があればする」というスタンスでいると、上手くいきやすいのが人志向です。
城志向の生徒が成績アップする学習法
- 自分の思うようにさせる
- ときどき進捗確認
- 軌道修正してあげる
城志向は、何を言っても結局は自分の思うやり方でしかしません。
「まずは自分の思うようにやってみな」と伝えると、喜んで自らやります。
ただ、「どこまで進んだ?」「今は何をやっている?」と、進捗状況をたまにチェックしてあげることが大切です。
自己流で進めているうちに自分のなかで勝手にストーリーが出来上がって「先生はそんなこと教えてないよ」というような勘違いや思い込みをしている場合が多々あるので、時々軌道修正をしてあげる必要があります。
あとは自由に放っておくのがいいですね。
大物志向の生徒が成績アップする学習法
- 基礎を端的に掴ませ
- 中レベルの問題でアウトプット
- 感覚で掴んだところで、間違えた問題についてもう一度基礎に
大物志向の生徒は基礎が大嫌いで、いきなり発展問題に手を出そうとする傾向があります。
他人ができないことをやりたいし、飽きやすいところがあるため、基礎よりも発展性のあるものを好むんです。
大物志向の生徒には「気持ちはわかるけど、基礎は大事だよ」と伝え、基礎が端的にまとめられていて感覚でつかめそうな本や資料を渡すといいです。
あとは、中レベルの問題でアウトプットさせます。
ひとつずつ積み上げていくよりも、実践しながら落とし込んで身につける方法が大物志向には合っています。
すごく貴重な情報をありがとうございます!
「30年の教師経験 × 個性學アドバイザー」という独自の経歴をお持ちだからこそ生まれた
3分類ごとの学習法ですね。
慈光先生の塾で勉強したら、成績がぐんぐん伸びそうですね…すごいです!

個性學を学ばないなんて、デメリットしかない
個性學を実践して、本当にたくさんの成功事例を経験されているのですね。

慈光さん:
個性學を使った成功事例は伝え切れないほど、実はもっとたくさんあります。
面談時の生徒とのコミュニケーションの質も格段に向上しましたし、進路指導の質や合格実績も向上しています。
保護者との関わり方も変化しました。
個性學は、人間関係が存在するあらゆる場面で使えますから、個性學を学ぶメリットは計り知れません。
「個性學が出来上がった以上、これを学ばないことはデメリットしかない!」くらいに感じています。
個性學が深いと感じるのは、よくある適性診断のように「あなたはこうゆうタイプですよ」というレッテル貼りで終わるのではなく、
「だからどうするの?」というその先があることです。
「ムスビ」です。
自分や周囲の人の12分類を知っても、それはまだほんの入口。
「あの人はこうだよね」とジャッジしている段階では、個性學の深さはまだ全然わかっていないんですよ。
個性學を深く理解している人同士が会話をすると「ムスビ」が起こります。
個性學を学ぶならここまで到達しないと意味がない。
自分や周囲の12分類だけ知ったところで終わらせるのは、本当にもったいないと思います。
お母さんたちに個性學を理解してもらう重要性
子どもは親の影響を受けている
10代の子たちは、個性が顕著にあらわれているものですか?

慈光さん:
いろいろなケースがありますが、子どもは親の影響がすごく大きい。
面談をしていても、子どもたちの本音を引き出すことは実はすごく難しいんですよ。
自分の本音をわかっている高校生はそんなにいません。
親から言われていることや環境で決めている子が多い。
親子の個性にギャップが大きいこともある。
だからうちの入塾申込書には、親の生年月日も書いてもらっています。
子どもの話を聞いていて「なんかおかしいな…」と感じた時は、親の個性を見てみます。
そうすると、親の個性の影響を受けている部分を察することができますね。
僕は以前は、弱者である子どもの気持ちに寄り添って「よし、先生が親と戦ってやる!」みたいなスタンスだった時期があったんですよ。
でも個性學を学んでからは、子どもと親のギャップを埋める、繋いであげる、結んであげる。そういった架け橋の役割にと思うようになりました。
どの親も、基本的には子どもの幸せを願っていますから。
親の悩み…原因のほとんどは親自身の個性にある
慈光さん:
それに、親の悩みって、ほとんどは自分の個性が原因なんです。
例えば「子どもが自分で宿題をせずに、いつも私に聞いてくる。先生、なんとかならないでしょうか?」という悩み相談。
個性を見てみると、このお母さんは城志向なんです。
悩みの正体は、家にいると子どもに毎日宿題のことばかり聞かれて、自分の家事や用事のペースが乱されてイライラしている。
だから「なんとかならないでしょうか?」と聞いてくる。
「城志向だから、そのように感じるんですよ」と伝えます。
そうするとお母さんは、納得してゲラゲラ笑って帰っていきますね。
「あ、私の問題か」と(笑)。
個性學を活用すると、お母さんが、自分自身の問題と子どもの問題を分けて考えられるようになるから非常にありがたいです。
個性學は真理!これからの「私教育」に必須
最後に、慈光さんは教育に長年携わってきて
教育現場には個性學が広まるといいなとお考えですか?

慈光さん:
僕は、「私教育」には、個性學は絶対必要だと思っています。
教育には2つあります。
国の中で生きていくために最低限必要なことを教える「公教育」と、それ以外の場「私教育」です。
どちらも必要なもので、学校教育は「公教育」、塾は「私教育」です。

「私教育」は、学校教育の補助的な役割ではありません。
私教育の本来の役目は…
- 生涯続く勉強への取り組み方
- 笑顔で努力できる子をどう育てるか
- 自分なりの付加価値に、いかに磨きをかけるか
江戸時代に全国にあった「寺子屋」は私教育でした。
日本が当時、他国とは違って植民地にならないほどの高い賢さを誇っていたのは、私教育の影響が大きかったんです。
私教育が役目を全うするには、個性學以上のツールはありません。
「私教育」で個性學を活用して、それぞれの個性に合ったやり方を教えてあげる。
「これが自分のやり方だ」ってわかれば、子供たちはやりますから。
もちろん「公教育」でしか得られない資格や信頼などがありますから、「公教育」「私教育」どちらも大切です。
お母さんがそのあたりのバランスを取れる賢さを持ってないといけないし、お母さんが個性學を知っているか知らないかは、すごく大きいと思います。
だから今は、お母さんたちに個性學を知ってもらおうと尽力しています。
お母さんたちが輝けば、子どもも輝きますから。
お母さんが動くと、お父さんも自動的に巻き込まれますしね(笑)。
最後にここだけの話ですが、
寺の住職として私が普段から感じていることと、個性學の内容は共通するものがあります。これには驚きました。
どちらも自然の摂理に基づいている。
個性學は真理だと思いますよ。
慈光さん、大変貴重な事例や体験談をありがとうございました!
「3分類を知っているか、知らないか」が、子どもたちの未来に大きな影響を与える可能性を実感しました。
「私教育」において、慈光さんのように個性學を実践する先生が増えたら素敵ですよね。
これからのご活躍も楽しみにしております。